インテリアコーディネートのポイントとは?
色の組み合わせ方を紹介
公開日:2025/10/28 / 最終更新日:2026/02/12

家具選びは、室内のインテリアや建具などの雰囲気と調和させることで統一感が生まれます。
たとえば、寝室のようにくつろいだり休んだりするためのスペースには派手な色を避け、入眠や休息に適した色を選びます。
インテリアは一色だけでなく、複数の色を組み合わせるのが一般的です。
異なるトーンや配色の組み合わせは心理的に落ち着きにくいため、色のもつ意味や心理的な作用を考えて、部屋に適した組み合わせを考えるとよいでしょう。
この記事では、店舗で家具を購入する際の選び方やメリット、通販との違いを紹介します。
インテリアは色の組み合わせが大切
インテリアにおいて、配色は空間の印象や居心地に大きく影響する要素です。
色は人の心や意識に訴えかける力があり、温かさやリラックス効果、静かで整った雰囲気などを視覚的に左右します。
色の選び方や配置を意識することが快適な生活空間づくりには欠かせません。
インテリアで使用する色は多すぎると統一感がなくなり、視覚的に雑多な印象を与えてしまいます。
基本的にはベースカラー・メインカラー・アクセントカラーの3色までに抑えるとよいでしょう。
「ベースカラー」は、壁や床などの大きな面積を占める部分で、空間全体の基本となる色です。
「メインカラー」は、ベースカラーを基調にした主要なアイテムの色味です。
家具やカーテンなど、ベースカラーの次に大きな面積を占める部分、または目につきやすいアイテムの色がメインカラーになります。
この部分の色味を意識的に整えると統一感やまとまりを与えます。
「アクセントカラー」は、名前のとおりアクセントとして取り入れる色を指します。
ソファーのクッションや棚の上に飾る小物、壁にかけるアート(絵)のように、部屋の主要部分以外に取り入れます。
たとえば、白やグレーが基調の空間にアクセントカラーとして赤、グリーンのような色を差し色にすると、メリハリや個性が演出できるでしょう。
ベース・メイン・アクセントの3色構成で部屋づくりを行うと、視覚的に偏りが少なくバランスのとれた空間になり、心理的に落ち着きを感じやすくなります。
さらに、それぞれの色の明度・彩度を調整すれば、空間の広がり・重さ・温度感といった細部の印象までも調整できます。
色が持つ特性とは
色には、広さ・温度・時間・重さといった要素を変化させる特性があるため、視覚的な効果を知ることが大切です。
広さの変化
色は、空間の広さ・狭さを視覚的に変化させる効果をもっています。
明るい色やホワイト系は光を反射する性質があることから、壁や天井に用いると部屋を広く見せられます。
物理的に狭い空間では、この特徴を踏まえて明るい色味をベースカラーなどに選ぶのが一般的です。
反対に、暗い色や深みのある色は光を吸収するため、空間を引き締めて落ち着きを感じさせます。
ただし、あまりにも暗い色合いでコーディネートしてしまうと密閉感を感じやすくなるため、心理的な影響を考慮して配色を考えなければなりません。
ブルー系の寒色は、遠近感の中で遠くに感じさせる効果を持つ色(後退色)として知られています。
明るい色やホワイト系のような光の反射を使わずに広がりを演出できます。
赤やオレンジの暖色は、寒色とは反対に近さを感じやすい色(進出色)です。
前に出て見える視覚効果があるため、空間に取り入れすぎると圧迫感が出やすく、差し色として使うのがおすすめです。
温度の変化
それぞれの色がもつ温度感も、部屋をコーディネートする際に欠かせないポイントです。
暖色は視覚的に温かみを感じさせ、部屋に温もりや元気な印象を与えます。
寒色は涼しさ・清涼感を与え、暑さにも負けない快適な雰囲気や清潔感を演出します。
たとえば夏に寒色、冬に暖色をメインカラーとすることで、視覚的な温度感から快適な空間づくりができるでしょう。
時間の変化
色は、人がもつ時間感覚にも影響するといわれています。
暖色は、実際の時間よりも緩やかに時間が経過するような効果をもつ色です。
暖かさを感じる温度の心理効果によりリラックスさせ、時間感覚を緩やかにする効果が期待できるのです。
一方、寒色は時間の流れが速く感じられる色といわれています。
仕事や作業を行う部屋に寒色を取り入れると、滞在時間を早めようとする心理効果が期待できるため、手を止めずに集中したい場合に適しています。
暖色と寒色の効果に加え、季節や日光の強さによる色の見え方にも注意しましょう。
朝から夜までの24時間で色味が変化することも考慮し、部屋ごとに適した色選びを意識してみてください。
重さの変化
色はものの重さや質感にも影響します。
暗い色や深みのある色は重厚で、存在感のある印象を与えます。
重たくなりすぎないように組み合わせには注意が必要ですが、書斎のインテリアや来客用の家具などに取り入れるとぐっと空間が引き締まり、高級感を演出してくれるでしょう。
明るい色や淡い色は軽快で、浮遊感や優しさを感じさせます。
子ども部屋に取り入れると、子どもの活発で柔軟な雰囲気やライフスタイルにマッチしやすく、圧迫感を和らげるため、お子さんにとっても安心感を与えます。
インテリアの色を組み合わせる際の黄金比率は70:25:5
インテリアの色を組み合わせる際は比率にこだわることで、バランスのとれたコーディネートに仕上がります。
ベースカラー・メインカラー・アクセントカラーをそれぞれ70:25:5の割合にするとよいとされていますが、カラーごとのポイントをみていきましょう。
ベースカラー(70%)
ベースカラーは空間の多くを占めるため、部屋の第一印象に直結する色です。
一般的には部屋の広がりや快適さを表現するために、ホワイト系やベージュ・ライトグレーのような落ち着きのある色が選ばれます。
シンプルでも飽きのこない色を使用することが、部屋を快適に演出するポイントです。
メインカラー(25%)
メインカラーは部屋の中でも目立ちやすい部分に取り入れる色です。
大きな家具やカーペットのほか、建具や造作家具にメインカラーを配置することもできます。
全体の25%をメインカラーで占める場合、個性を出しすぎるとメインカラーだけが浮いてしまうため、ベースカラーとの調和を意識してみてください。
アクセントカラー(5%)
アクセントカラーは、小物や一部分に取り入れるごくわずかなアクセントです。
ベース・メインで調和させたところに、ワンポイントのアクセントとして取り入れるため、部屋が個性的かつオリジナリティのある雰囲気に仕上がります。
インテリアの色を組み合わせる際のポイント
ここでは、インテリアの色を組み合わせる際のポイントをみていきましょう。
ポイント①インテリアのテイストを決める
はじめに、インテリアの「テイスト」を明確にしましょう。
テイストとは、「ナチュラル」「モダン」「和風」といった、部屋全体から生み出されるデザイン的な特徴です。
「ナチュラル」を選ぶ場合は、木の温もりやベージュ系・アイボリー系のような優しい色合いを中心に、自然の風合いを取り入れて統一します。
「和風」は、和を感じる色味に加えて、竹・い草のような素材を選ぶと、和風らしい雰囲気に仕上がります。
ポイント②無彩色か有彩色かを決める
次に、無彩色(白・黒・グレー)または有彩色(赤・青・緑のように彩度をもつ色)の取り入れ方を決めます。
無彩色は奇抜さや慌ただしさがなく、落ち着いた雰囲気を与え、どんな家具・家電・小物とも合わせやすい色味です。どちらかに統一するコーディネートも魅力的ですが、無彩色と有彩色のバランスをとって両方を組み合わせる方法も、心地よい空間づくりのポイントです。
ポイント③ベースカラー・メインカラー・アクセントカラーの3色を決める
インテリアコーディネートでは、ベースカラー・メインカラー・アクセントカラーをそれぞれ決めたうえで、黄金比率を考えて取り入れましょう。
ベースカラーにメインカラーを調和させて、ポイント的にアクセントカラーを用います。
メインカラーやアクセントカラーの比率が大きくなりすぎないよう、黄金比率を意識することが大切です。
ポイント④類似色と補色を決める
色の関係性を踏まえて、選んだ色味の隣接する色である「類似色」や、反対側にある色相の「補色」を取り入れることもできます。
たとえば、ブルーを中心とした寒色をメインカラーにする場合、青の類似色は紫です。
ブルーがメインの部屋づくりに紫を類似色として採用すれば、色同士が浮いて見えすぎず、まとまりが出しやすくなるでしょう。
「補色」は、色同士の関係性をまとめた色相環と呼ばれる図のうち、反対に位置する色同士の呼び名です。
たとえば、レッドの反対にある色はグリーンであり、イエローの反対にある色は紫です。
反対側にある色相はアクセントカラーに適しており、空間に華やかさや個性を添えられます。
心理効果による色の選び方
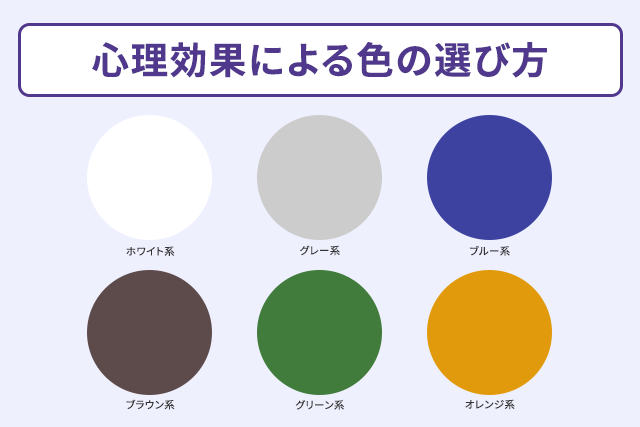
色にはさまざまな心理効果があり、広さや重さ、時間の流れのほかにも、色がもつ特有の心理効果があります。
ここからは、ホワイト系やブルー系といった色のもつ特徴をチェックしていきましょう。
ホワイト系
ホワイト系の色味は、清潔感・広がり・明るさを感じさせる色です。
心理的には、無難な(奇抜すぎない)雰囲気やリフレッシュ効果を与え、他の色とも組み合わせやすいため、どの部屋にもマッチします。
キッチンや浴室といった水回りでは清潔感を、リビングやエントランスでは広がりを出すことで、快適かつ過ごしやすい空間づくりに役立てられます。
家具にホワイト系を取り入れる場合は、汚れが目立つことを考えて汚れを落としやすい素材を選ぶなどの工夫が必要です。
グレー系
グレー系は黒と白の中間色で、中立的な色味としての安定感や落ち着きを表現します。
奇抜さがなく他の色を引き立てる効果もあるため、ベースカラーやメインカラーとして取り入れやすい色です。
一方で、グレーにはライトからダークまで段階があるため、暗すぎるグレーが面積を占めると重苦しい印象になりやすく、ネガティブな心理作用が生まれやすいデメリットがあります。
中間色としてのメリットを活かすときは、ベースカラーではなくメインカラーにしてアクセントカラーで部分的に明るさを出したり、刺激を少なくしたい部屋に取り入れたりするとよいでしょう。
ブルー系
ブルー系は寒色の爽やかさ・冷静さ・時間感覚を短くして集中力を高める心理効果が期待できる色です。
レッドやオレンジなどの暖色が興奮作用をもたらすのに対し、ブルー系は心を落ち着かせてくれるため、ストレスを和らげたい空間(自室や仕事場)にも向いています。
ブルー系は彩度や明度によって表現できる雰囲気が変わるため、重厚さが欲しい空間には濃いブルーが適しています。
淡いブルーは涼しげで、空間に広がりが生まれ、目にも優しい色合いです。
ブラウン系
ブラウン系はナチュラルテイストに多く取り入れられる色で、温かみ・安心感・親しみやすさを感じさせる色とされています。
カフェスタイルや和風、北欧などのあらゆるテイストにマッチし、濃い色味は重厚感を与え、高級な雰囲気を演出します。
濃い色は空間を引き締めますが、ブラウン系は黒のように重たくなりすぎないため、やや濃い色味でも暗くなりすぎない点がメリットです。
一例として、ダイニングにブラウンカラーのテーブルやチェアを置けば、安心感や親しみやすさを感じながら食事が楽しめるでしょう。
グリーン系
グリーン系は自然や健康を想起させる色で、ナチュラルテイストや和風とも組み合わせやすい色です。
レッドやオレンジ、イエローのような明るさはなくても、目に優しいため長時間過ごす場所の配色に適しています。
ブルー系では寒々しくなりすぎる場合は、グリーン系を選べば爽やかさや自然な雰囲気が演出できるでしょう。
リラックス効果や穏やかな雰囲気もあるため、暖色が苦手な方におすすめの色でもあります。
たとえば、ソファーやカーテンにメインカラーとしてグリーン系を採用すれば、ベースカラーと調和しながら爽やかな部屋に仕上がるでしょう。
オレンジ系
オレンジ系はいきいきとした活力や陽気さ、前向きさを感じさせる色です。
元気・健康・行動意欲の刺激といった心理作用が期待できるため、人が多く集まる場所や交流スペースへの配色に適しています。
家族や友人が集まるダイニングスペースやインナーテラスなどに向いており、小物や観葉植物、絵画として飾っても存在感を発揮します。
明度や彩度が高いものは興奮作用があるため、アクセントカラーとして取り入れると効果的です。
インテリアは色の特性で組み合わせを選ぶ
いかがでしたでしょうか?
今回は、インテリアに取り入れたい色の特徴や色がもつ特性、組み合わせのポイントを紹介しました。
部屋のコーディネートを考えるときは、どんなテイストにしたいかを考えてから、アイテムを配置します。
新しい家具を買い足す際にも、ベースカラー・メインカラー・アクセントカラーの3色を意識すれば、まとまりのある部屋ができあがります。
理想的な部屋づくりのために、色の特徴や心理効果を取り入れて検討するとよいでしょう。
東京にある日本最大の家具店村内ファニチャーアクセス八王子本店で皆さまをお待ちしております。
家具選びでお悩みの際は、専門のスタッフが皆さまの家具選びをサポートさせて頂きます。
ぜひ東京で家具屋をお探しの方は、村内ファニチャーアクセスまでご相談ください。